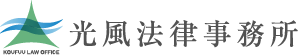小説「激しく煌めく短い命」
週末に綿谷りさ著者の新刊「激しく煌めく短い命」を読んだ。
途中で読むのを止められなくなり、夜中の4時までかかって読み通し、最後は目の奥がズキズキ痛んだ。
それだけでなく、次の日もう一度読み返したくなり、本を開くとまたもやぐいぐい引き込まれ、夜明けまで読みふけった。目を使いすぎて視界に幕がかかったようになり、それ以降ずっと目の調子が悪い。
そのぐらいパワーのある作品だった。
この小説は2部に分かれていて、第1部では主人公久乃(ひさの)とその女友達の綸(りん)の13歳の時が描かれている。
「山根くんと綸、どっち見ているときの方が、自分がドキドキしているか、わかりすぎて辛い。」
優等生で自分の感情をあまり表に出さない久乃にとって、天真爛漫でクラスでも人気者の綸は「友達」でありながら、それを越えた存在。
強い吸引力と安心感、それ故に彼女への思いが自分を既定路線から外れさせて戻れなくさせるのではないかという不安感を同時に抱かせる存在。
惹かれ合い、平凡な、また非凡なたくさんの時間を積み重ねて心の奥を開いて、二人は触れ合っていく。いじめや差別、家族からの締め付け、何よりも自分の中にある世間の目に掬い取られて、やがて二人は離れ、卒業式では取っ組み合いになり血を流すという壮絶な衝突を経て、関係は完全に断絶する。
第二部では 2人が32歳になって再会した時が描かれる。
「改めて綸を見つめるけど、目の前のこの人があの綸だとは、まだ信じられない。失礼な表現になってしまうけど、大人になった綸は荒んでる。」
エリートを目指して猛勉強して進学校に入ったはずなのに、いつしか枕営業にまで手を出して都会で孤独に戦う久乃、一方で、自由に生きることが信条だったはずの綸は、年下の薄情な男に翻弄されながらも結婚を諦めきれずしがみついている。
そこには何者にもなれるはずの輝く未来を持っていた二人の少女が、結局、何者にもなれなかった残酷な現実があり、その再会のシーンは胸が抉られるような痛みがある。
目を背けて、人生こんなものだ、これも十分幸せなんだと自己洗脳していた二人が、再会によってそれぞれその現実を見据えて、踏み出していく。
心に残ったシーン。
久乃が営業の仕事で枕営業していることを打ちあけたときに、綸が、自分も以前にホステスをやっていた時は周りでそういうことをしている人がいたと話し、「自分はやってへんかったけど、根性あるなぁと思っていた。女はそういう技を使って成り上がっていくのも、1つの有効な手やんな」とむしろ励ましてくれるところ。てっきり軽蔑されるだろうと思っていたのに、軽く受け流されたことに久乃はホッとするのではなく、「心に穴が開いて、そこから水が少しずつ流れ出て行くようだった。私は綸に何を期待してたんだろう。
涙が溢れてくる。そして言う。綸に自分の枕営業を止めて欲しかったんだと。
戸惑って「そんなん、他人に言われることやなくて、自分で決めることやで」と至極真っ当な答えを返してきた綸に対して、「うん、わかってる。気にしないで」と答えるが、その様子をみた綸がしっかりと久乃の両肩を掴んでおでこを合わせ、真剣な眼差しで「もう誰とも寝たらアカン」と言葉をかけてくる。
正しいことを言って欲しいわけじゃない、間違ったことをしてもそこにはそうなるだけの経緯や過去がある、それをわかって抱きとめて欲しいという気持ちを他者がすくい取ってくれる奇跡なような瞬間がまぶしくて胸が熱くなった。
私も13歳の頃、誰にも言えない心を見せることができた友達がいた。私のダメさ、弱さ、狡さをジャッジせず、その奥にあるもの受け止めてくれる女の子だった。
帰国子女であることを理由に私がクラスの中で浮き上がり、クラスの一軍のグループからいじめられた時、人前でろくに話もできないような大人しい彼女が、「そういう言い方やめへん?」と静かに庇ってくれた。
自分が標的になることを一瞬たりとも考えずにさっと私の前に出たその潔さ、強さに驚いた。そんな人は初めて見た。いじられることを自分でも面白がるフリをして平気な顔して笑ってみせていたのに、彼女は私の笑顔の下にある心を分かってくれた。年齢ではないんだなぁと思った。大人でもわからない人がいる。子供でもわかる人がいる。
数年後、はっきりともう私とは一緒にはいられないと言われ、彼女は離れていった。どんなに懇願しても聞き入れられなかった。私が暴力的に寄りかかりすぎたせいだった。彼女はいわゆる宗教2世で、親が信仰していた宗教の問題も絡んでいたと思う。
この小説の久乃のと同じように、年月が経っても彼女のことはずっと忘れられない。彼女の飼ってる犬を引き連れて夜の校庭を探検に出かけ、誰だ!と警備員に追いかけられたこと、マラソン大会に向けて練習しようと毎朝、山の麓まで出かけるのに、気がつくといつも手をつないで夢中で喋りながらただ歩いていたこと、私から離れていくと決めた彼女に対して謝ろうとして自宅に行って彼女の顔を見た途端、気持ちがはじけてなぜか平手打ちして逃げたこと、絶交されたあと一度度だけ彼女から近寄ってきたことがあり、それは私が1人で孤独に下校する後ろ姿を見て追いかけてきて一緒に黙って並んで歩いたこと。
お寿司が好きだった彼女に今、お腹いっぱい東京の美味しいお寿司をご馳走できたら、どんなに嬉しいだろうと思う。同時に、彼女のことを思い出すと置き去りにされときの、自分が汚れて、無価値に感じた痛みも思い出す。
自分の人生から立ち去った人のことを忘れられないということは苦しい。その時間に絶対に戻れないこと、取り戻せないことをいつも思い出させる。
この小説には、忘れられないということの静かな痛みが描かれている。誰かと心の奥でつながり、触れ合うことは、まさしく人生がきらきらっと「きらめく」瞬間であり、記憶に刻み込まれる。その人を失った後はそれは痛みの記憶だ。
でもそれこそが生きている証であり、このタイトル通り、限りある命を輝かせるものなんだなと思う。
読み終わった後も何かがゆっくり静かに燃え続けるような感覚が続く素晴らしい小説だった。
松田恭子